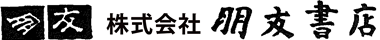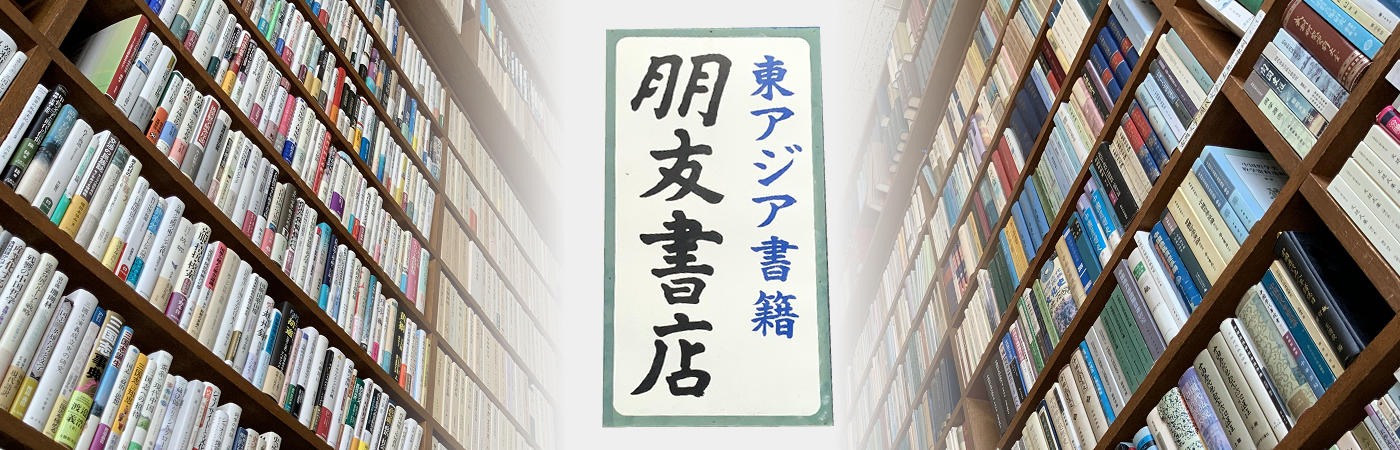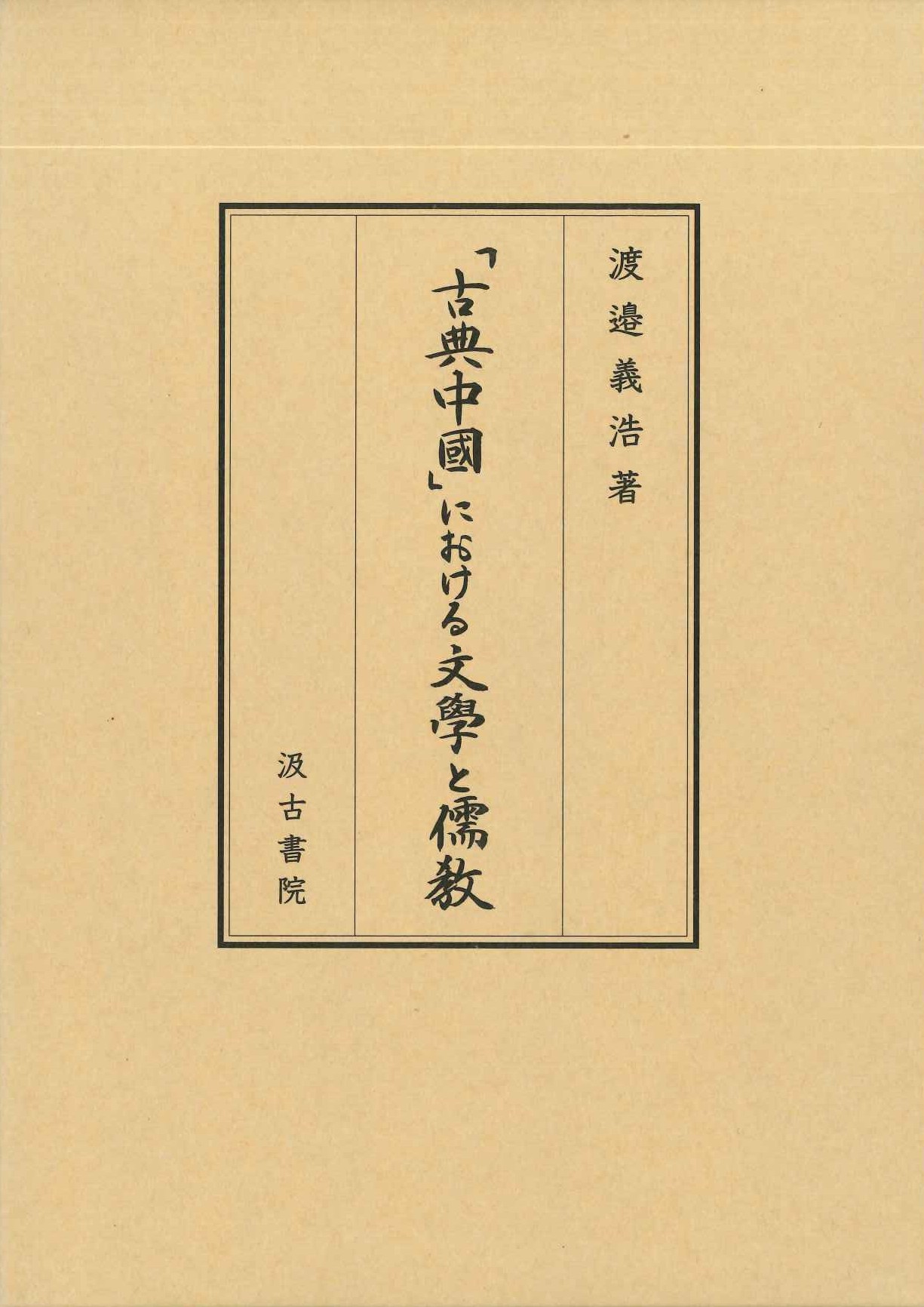日本
「古典中国」における文学と儒教
日本
「古典中国」における文学と儒教
- 出版社
- 汲古書院
- 出版年月日
- 2015.04
- 価格
- ¥8,800
- ページ数
- 335
- ISBN番号
- 9784762965463
- 説明
- ※出版年が古いので新本ですがヤケ・シミ・痛みがございます。
中国文学史上における六朝文学の位置を儒教との関わりの中で明らかにする。
【序章】より(抜粋)
なぜ、中国では、科挙という官僚登用制度において「文学」を重視したのであろうか。「文学」に人を統治することを可能にする人間性が表現されているのであろうか。「文学」を基準として、本格的に官僚を登用しようと試みた者は、曹魏の基礎を築いた曹操である。曹操は、郷挙里選を批判するなかで、郷挙里選の根底、そして三国時代の知識人である「名士」の根底にも置かれていた儒教に対抗する新たな文化的価値として「文学」を宣揚し、建安文学を興隆させた(本書第三章)。かかる新しい発想は、曹操個人の資質のみに依拠しない。曹操が活躍した後漢末は、後漢「儒教国家」の衰退を期に、「古典中国」が新たな展開を始める変革の時代の幕開けであった。
「古典中国」とは、「儒教国家」の国制として、後漢の章帝期に白虎観会議により定められた中国の古典的国制と、それを正統化する儒教の経義により構成される。のちの中国に継承される理想的国家モデルである「古典中国」の形成に大きな役割を果たした王莽の新は、わずか十五年で滅びた。それにも拘らず、新を滅ぼした後漢は、王莽の国制を基本的には継承し、それを儒教の経義と漢の国制とに擦り合わせ続ける。その結果、後漢で成立した「古典中国」は、儒教の経義より導き出された統治制度・世界観・支配の正統性を持つに至るのである。こうした「古典中国」が新たな展開を見せようとする変革期において、「文学」は「古典中国」にどのような位置づけを得ることにより、科挙の主要な試験科目となるに至ったのであろうか。
また、中国における「文学」が、科挙の試験基準となるような人間性の表現を本質とし、また、時の国家と強い関わりを持つ政治性を帯びるものであるならば、今日的な意味における文学表現は、第一義に置かれるものではなかったのであろうか。表現された「文」そのものに美しさを求め、あるいは、いかに書くのかという表現技法を磨き、さらには、抒情や思想を表現していく、という今日的な意味での文学意識に基づく表現活動は、国家や儒教との関わりの中で、どのように展開されたのであろうか。本書は、こうした問題関心に基づき、「古典中国」における「文学」のあり方を儒教との関わりの中で探求していくことを目的とする。